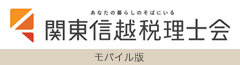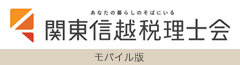�ŗ��m�ɂ���
�ŗ��m�ɂ���
���c�v�]����
����25�N�x�Ő��y�ѐŖ��s���Ɋւ��錚�c��
[1] �͂��߂�
�����Q�R�N�R���P�P���ɔ������������{��k�Ђ͓��{�ɖ��\�L�̔�Q�������炵���B����͕����ʂ���łȂ��l�X�̐S�̒��ɂ��傫�Ȓ܍����c�����B
���̍���ɗ������������߂ɂ́A���{�S�̂��ЂƂɂȂ���{�l�����܂łɔ|���Ă����p�m���W�߁A�ЂƂ�ЂƂ肪���������̏o���邱�Ƃ��o����͈͂ŕ����̂��߂ɋ��͂��Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
�����͒P�Ȃ�ЊQ�����ł͂Ȃ��A���͂�����{�����߂����߂ɖ���������ɓ��ꂽ���{�I�Ȃ܂��Â��肪�K�v�ł���B
���{�o�ς͒������f�t����k�Ђ̉e���A�ߓx�ȉ~�����ŗ�������̒����������Ȃ��܂܃��[���b�p�̌o�ϊ�@���ǂ��ł����|���Ă��܂����B
���{�����̐��Y�ƗA�o�̗������݂��~�܂炸�A�ݔ������̌����A��Ǝ��v�̈����������ٗp�̑��i���i��ł��Ȃ��B�l����͗₦���܂܂̂Ȃ��A�łƎЉ�ۏ�̈�̉��v�̂��Ə���ł̐ŗ����グ���悤�Ƃ��Ă���B
���̂悤�Ȍ����������̂Ȃ����̊�ՂƂȂ�Ő����ǂ�����ׂ�����^���ɋc�_���A�o�ρE�Љ�̕ω��ɑΉ���������ׂ��Ő����\�z���Ă����Ȃ���Ȃ�Ȃ��B
[2] ��{�I�ȍl�����ɂ���
�ŗ��m�@�ł́A�u�ŗ��m��́A�Ŗ��s�����̑��d�Ŗ��͐ŗ��m�Ɋւ��鐧�x�ɂ��āA�����̂��銯�����Ɍ��c���A���͂��̎���ɓ��\���邱�Ƃ��ł���B�v�ƋK�肳��Ă���B���̋K��Ɋ�Â��A�e�ŗ��m��ł́A�����������I�ȐŐ��̊m���Ɛ\���[�Ő��x�̈ێ��E���W��ړI�Ƃ��āA�Ő������Ɋւ��錚�c���N�쐬���Ă���B���̊�{�I�ȍl�����͈ȉ��̂Ƃ���ł���B
(1)�����Ȑŕ��S
(2)�����Ɣ[���̂ł���Ő�
(3)�K�v�ŏ����̎������S
(4)����ɓK������Ő�
(5)�����ȐŖ��s��
[3] ���c���̍\���ƊT�v
�֓��M�z�ŗ��m��i�ȉ��A�u�{��v�Ƃ����j�̌��c�v�]�́A��{�I�ɑO�N�x�����Q�l�Ƃ��A���������W�������ڂ𒆐S�ɖ{����������ɂ����Ď��܂Ƃ߂��s���A������ɂ�����R�c���o�Č��\���Ă���B�Ȃ��A�u�Ő�������j�v���Ɏ��グ��ꂽ���ڂ�ڍׂȌ����̏�ŐV���Ȉӌ��`�����K�v�ȍ��ڂɂ��ẮA���c���ւ̌f�ڂ������킹�Ă���B
�{���c���́A52���ڂ̗v�]�ɂ��āu�Ő��Ɋւ��錚�c�E�v�]���ځv�A�u�Ŗ��s���Ɋւ��錚�c�E�v�]���ځv�ɑ�ʂ�����ŁA�Ő��Ɋւ��ẮA�Ŗڂ��Ƃɕ��ނ��Ă���B�T�v�͈ȉ��̂Ƃ���ł���B
���Ő��Ɋւ��錚�c�E�v�]����
[��] ���Œʑ��@�W�i�X���ځj
�@���[�Ŏ҂̌����̕ی��}��A�Ŗ��s���̓����������߂���e�̍��ڂ������Ă���B
�@�@�E�[�ŎҌ������͂̑�������
�@�@�E�㔭�I���R������ꍇ�̍X���̐�����������
�@�@�E�s���\���Ă̌��薔�ٌ͍�������܂ł̒����P�\
�@�@�E�k�y�ېŋ֎~�̋K��̐V��
[��] �����Ŗ@�W�i14���ځj
�@�����Y�����E���n�����W
�@�@�E�y�n���̏��n�����̑��v�ʎZ�y�ьJ�z�T����F�߂邱��
�@�@�E���Ɨp���Y�̏��n������K�v�o��ɎZ��
�@�@�E��ꊔ���ɌW����n�����̌J�z���Ԃ��������邱��
�@�����^�����W
�@�@�E���^�����҂ɂ��Ċm��\���������Ƃ��A�N�������͑I�𐧂Ƃ��邱��
�@���͏o�E��o�����̊W
�@�@�E���Y�������̒�o�p�~
[�O] �@�l�Ŗ@�W�i�S���ځj
�@�E�������^�̒�����z���^�̔p�~
�@�E���۔�ېł̔p�~
[�l] �����Ŗ@�E�@�l�Ŗ@���ʊW�i�R���ځj
�@�E�d�b�������ɂ��Č������p���Y�Ƃ��ď��p���\�Ƃ��邱��
[��] �����Ŗ@�W�i�U���ځj
�@�E�ېŕ����������Ȉ�Y�擾�ŕ����ɉ��߂�
�@�E�A�є[�t���x�̔p�~
[�Z] ����Ŗ@�W�i�S���ځj
�@�E�ȈՉېœ��̓K�p�ɂ��ē��Y���ƔN�x�̉ېŔ��㍂�Ɋ�Â�����Ƃ��邱��
[��] �n���ŊW�i�W���ځj
�@�E�l���Ɛł̎��Ǝ�T���z�̈����グ
�@�E�Œ莑�Y�ŁE�s�s�v��łɂ��ĕ]���̓K������}�邱��
���@�Ŗ��s���Ɋւ��錚�c�E�v�]���ځi�S���ځj
�E�����ʒB���܂ߖ@�߉��ߒʒB�����ׂČ��J���邱��
�Ő��Ɋւ��錚�c�E�v�]����
[��] ���Œʑ��@�W
[1] �[�ŎҌ������͂𑁊��ɐ��������邱�ƁB�i�V�K�j
�i���R�j
�[�Ŏ҂̌����m�����邽�߁A����������v�]����B
���@��R�O���Ɂu�[�ł̋`������K�肳��Ă���B�܂��A���@�O���ɂ́u�����匠�v��搂��Ă���B�[�Ŏ҂ł��鍑���ɂ͋`��������Γ��R�Ɍ���������B�[�Ŏ葱���ɂ��Ă��R��A�[�ŎҌ������͂Ƃ͌��������ł͂Ȃ��`�����K�肷����̂ł���B�킪���̐Ő��͍s�����̎����ɗ������K�肵���Ȃ������ł���[�Ŏ҂̎����ɗ����Ă��Ȃ��B
���ď�����؍��Ȃǂɂ��[�Ŏ҂̌����`�����K�肵�����x������ɂ�������炸�A��i���ł�����{�ɂ��܂����肳��Ă��Ȃ����Ƃ͐Ŗ��s����傫�Ȗ��ł���A�Љ�ۏ�Ɛł̋��ʔԍ��Ȃǂ̘_�c�Ƃ͊W�Ȃ������ɐ���������ׂ��ł���B
[2] �㔭�I���R������ꍇ�̍X���̐����������A���R�m��̓����猻�s�Q�����ȓ����P�N�ȓ��ɕύX���邱�ƁB�i�ʖ@�Q�R�A�j�i�p���j
�i���R�j
���̋K��́A�㔭�I�Ȍ��z���R�����������ꍇ�̔[�Ŏ҂̌����~�ϋK��ł���A���̖ړI��B�����邱�Ƃ��ł���悤�A�葱���Ԃ��\���m�ۂ���K�v������B�Q�����ȓ��ł͊��Ԃ�k�߂��邱�Ƃ����邽�߁A���Ԃ��������ׂ��ł���B
[3] �[�����̗�������Q�����o�߂������Ȍ�̉��ؐł̊����i�N�P�S�D�U���j�����������邱�ƁB �i�ʖ@�U�O��@�@�V�T�A���@�P�R�P�j�i�p���j
�i���R�j
���ؐłɂ́A�x���ɂ��s�������I����������B�������A�ߋ��ɗ�����Ȃ�������̏����Ă��A�P�S�D�U�������ɂ��Ă��A���������i����_�̊�N�����{�S���j�̂Q�{���x�̊�����K�p���ׂ��ł���B
[4] �ҕt���Z���̊�������{��s�@�K��̏��Ǝ�`�̊�����ɉ��߂�B�i�ʖ@�T�W�A�[�@�X�T�A�ʗ߂Q�S�j�i�V�K�j
�i���R�j
���{��s�@�ɂ���߂��Ă��鏤�Ǝ�`�̊�������ɔN�S���̊��������Z���������́A���݂̋�s�����̏����ӂ݂Ă����ɍ����ł���A���̂��ߒ��Ԕ[�t�Ō̈ӂɉߏ�Ȕ[�t���s���悤�ȃP�[�X���o�Ă��Ă���A��������������K�v������B
[5] �s���\���Ă������ꍇ�ɁA���̕s���\���Ă̌��薔�ٌ͍�������܂Œ�����P�\���邱�ƁB�i�ʖ@�P�O�T�j�i�p���j
�i���R�j
�ېŏ����ɂ��ĕs���\���Ă����Ă��Ă��A������P�\���Ȃ����߁A���̐ŋ���[�����܂łɊ��[���Ȃ���A���⍷�����Ȃǂ̑ؔ[�������s���Ă��܂��B���̕s���\���Ăɂ��Ă̌��薔�ٌ͍�������܂ł͒�����P�\���āA�s���\���Ă̎葱�ɏW���ł���悤�ɂ��ׂ��ł���B
[6] �ЊQ���ɂ������̉����̗��R�ɁA�u�ŗ��m�y�ѐŗ��m�������̍ЊQ�v�Ȃǂ̕����������邱�ƁB�i�ʖ@�P�P�j�i�p���j
�i���R�j
�����@�l�y�ьl�[�Ŏ҂́A�ŗ��m�������ւ̈˗��������傫�����߁A�[�Ŏ҂����łȂ����̊֗^������ŗ��m�������̍ЊQ���������̉����̗��R�ɉ�����K�v������B
[7] �ҕt����Ŋz�Ɣ[�t���ׂ��Ŋz���������ꍇ�A�ҕt���̏[����[�Ŏ҂��I���ł���悤�ɂ��邱�ƁB�i�ʖ@�T�V�j�i�p���j
�i���R�j
�[�Ŏ҂ɔ[�t���ׂ��ŋ��Ɗҕt���ׂ��ŋ����������ꍇ�ɁA�ېŒ��͊ҕt��������ɏ[�����邱�Ƃ��ł���|��߂��Ă���B�\���[�Ő��x���̗p���Ă���ȏ�A�[�Ŏ҂̑��ł��A�\���[�t���Ɋҕt���̏[����I�ׂ�悤�ɂ��ׂ��ł���B
[8] ���Ԑł̏ꍇ���܂߁A�k�y�ېŋ֎~�����̋K���݂��邱�ƁB�i�ʖ@�P�T�j�i�p���j
�i���R�j
�k�y���@�́A���݂̖@�K�ɏ]���ĉېł��s����Ƃ�����ʍ����̐M���𗠐�A���̌o�ϊ����ɂ�����\���\����@�I���萫�Ȃ����ƂɂȂ�B���Ԑł̂悤�ɁA���Y������ɂ�蒼���ɔ[�ŋ`�����m�肹���A���Ԃ̒��r�ōs��ꂽ�@�����̌�ɁA���Ԃ��I�����鎞�_�Ŕ[�ŋ`��������������̂ł����Ă��A�[�Ŏ҂͓��Y������̎��_�ɂ�����d�Ŗ@�K�ɏ]���ē��Y������Ɋւ���[�ŋ`������������̂ł��낤�ƐM������̂��ʏ�ł���ƍl�����A���̂悤�ȏꍇ�ɂ����Ă��A���̐M����ی삷��K�v������B
[9] �����ŁA�@�l�ŁA�����œ��ɂ����铯���W�҂Ƃ��Ă̋K��͈̔͂͏k�����ׂ��ł���B�i�@�߂S�A���@�Q�Q���j�i�V�K�j
�i���R�j
�����ŁA�@�l�ŁA�����œ��ɂ����āA�����W�ҋy�ѓ��ʊW�҂͈̔͂��߂�ꍇ�́A���@��̐e���T�O���ؗp����Ă��邪�A�Љ�ʔO��̐e���ϔO�Ƃ̊Ԃɂ͑����̘������F�߂���B�[�Ŏ҂̗\�����Ȃ��Ƃ���ŕs���̓K�p�͈͂ɊY�����Ă��܂��ꍇ������B
��������瘨�����邱�ƂȂ��ʊe���x�̎�|�ɑ������͈͂Ɍ��肷�邱�Ƃ��K�v�ł���B�������̂Ȃ��������̕]���ɍۂ��Ă̓����W�҂͈̔͂́A�z��ҁA���n�����A�Z��o���y�тP�e���������x���K�ł���B�e�ŋ��ʂ�����̂Ƃ��Ē�`�ł���Ƃ�����Œʑ��@�ɂ����z���邱�Ƃ��K�ł���B
[��] �����Ŗ@�W
[1] �s���Y�����E�G�������ׂ��Ɩ��p���Y�ɂ��Ă��A���Ɨp���Y�Ɠ��l�̎��Y�������x�Ƃ��邱�ƁB�i���@�T�P�C�j�i�p���j
�i���R�j
���Y�����͑O�N�ȑO�̏������z���C������@�\�����邽�߁A���Ɨp���Y�ȊO�̎��Y�ɂ��Ă��l�����ׂ��ł���B���Ƃɏ�����s���Y�����ł����Ă��A�Ⴆ�r�������ĐV�������Ƃ��s���Ȃǂ̏ꍇ�A���̎��Y�����͗����J�z�����ł��Ȃ��̂ŁA�~���悤���Ȃ��B
[2] �y�n�E�������̏��n�ɂ�萶���������ɂ��āA���v�ʎZ�y�ьJ�z�T����F�߂邱�ƁB�i���@�U�X�A�[�@�R�P�A�R�Q�j�i�p���j
�i���R�j
���v�ʎZ�́A�����̎�ނ��킸�K���ȒS�ŗ͂ɉ����ĉېł���Ƃ����A�ېŌ����̊�{���O���������邽�߂̐��x�ł��邪�A�y�n�������̏��n�����ɂ��đ��v�ʎZ�y�ьJ�z�T����F�߂Ȃ����Ƃ́A�S�ŗ͂������������ɑ��Ă��ېł��邱�ƂɂȂ�A�����ېłƑ����ېłƂ̎d�g�݂̍��͂�����̂́A�ېŏ�̖�肪����B
[3] ���Ɨp���Y�̏��n�����̏����敪��ύX���邱�ƁB�i���@�T�P�A�U�X�j�i�p���j
�i���R�j
�s���Y�����A���Ə����̎��Ƃ̗p�ɋ������Œ莑�Y�̎��Y�����́A�e�폊���̕K�v�o��ɎZ�������B�������A���n�����͏��n�����ƂȂ�A���v�ʎZ����������Ă���B���Ƃ�s���Y�o�c��p�Ƃ���Ƃ��ɂ́A���̎��Ƃ̗p�ɋ����Ă����Œ莑�Y�p���邱�Ƃ������B���̍۔���������n�����́A����܂ł̎��Ə�����s���Y�����̏C���A���Z�Ƃ��Ă̐��i��L����B���Ɨp���Y�̏��n�����́A���Ə������͕s���Y�����̕K�v�o��ɎZ�����ׂ��ł���B
[4] �F�\���̏������̌J�z�T�����Ԃ𑊓����ԉ������邱�ƁB�i���@�V�O�j�i�V�K�j
�i���R�j
�F�\���@�l�͌��݂X�N�̌J�z�T�����Ԃ��݂����Ă���A�������̊ϓ_�����������v�]����B
[5] ��ꊔ�����ɌW����n�����̌J�z�T�����Ԃ𑊓����ԉ������邱�ƁB�i�[�@�R�V�̂P�Q�̂Q�j�i�p���j
�i���R�j
�u���~���瓊���ցv�Ƃ�������ɂ��A�l�̎����������ւƗ��ꂽ���A�Q�O�O�W�N�̐��E�I�ȋ��Z��@�ɔ����������������\���ɂ��A�����̌l�����Ȃ�̑����������ƍl������B
���s�Ő��ł́A��ꊔ�����ɌW����n�����̌J�z�T�����Ԃ͂R�N�Ƃ���Ă��邪�A���̊��Ԃ𑊓����ԉ������邱�ƂŁA�l�����S���ē����������s������𐮂���K�v������B
[6] �u�y�n���̕����q�̋��z�́A�����Ŗ@��U�X���P���ɋK�肷�鑹�v�ʎZ�̑ΏۂƂ���Ȃ��v�K��́A�p�~���邱�ƁB�i�[�@�S�P�̂S�j�i�p���j
�i���R�j
�o�u���o�ώ��Ɏ{�s���ꂽ���̋K��́A�y�n�ُ̈�ȍ�����}�����邽�߂ɗ��@���ꂽ���̂ł���A���o�ω��ɂ����Ă͖{�K��𑶑�������K�v���͔F�߂��Ȃ��B
[7] �G���T���̑Ώۂɍ���̏ꍇ�ɂ�����Z�ቮ���̔R������܂߂邱�ƁB�i���@�V�Q�@�j�i�V�K�j
�i���R�j
����̏ꍇ�ɂ�����ቺ�낵��p�����G���T���̑ΏۂƂȂ邱�Ƃɑ��A����Z��ɂ�����Z�ቮ�����ቺ�낵��p���Ɠ��l�A�Ɖ��̓|���h�~���邱�Ƃ��ړI�ł���̂ŗZ��̂��߂̓������̔R������Љ�̕ω��i������̒l�オ��A����A�����̂ɂ�鍎��Z��̕��y�x�����j�ɍ��킹�G���T���̑ΏۂƂ��ׂ��ł���B
[8] �����Ŗ@�T�U���i���Ƃ���Ή�����e��������ꍇ�̕K�v�o��̓���j�A�T�V���i���Ƃɐ�]����e��������ꍇ�̕K�v�o��̓��ᓙ�j��p�~���邱�ƁB�i���@�T�U�A�T�V�j �i�p���j�i���R�j
�i���R�j
���n�݂��ꂽ���̋K��́A���т��ېŒP�ʂƂ�����̂ł���A�l�P�ʉېł������Ƃ��錻�s�̏����Ŗ@�̗�O�I�K��ł���B�e���Ɏx�����J����̑Ή��ɂ��ẮA���̎���ɉ����Čo�ϓI�������̊ϓ_���画�f�����ׂ��ł���A���v����ɂ���e���Ƃ��������ŁA�K�v�o��Z�����ے肳���ׂ��ł͂Ȃ��B
[9] ���^�����҂ɂ��Ă��m��\���������Ƃ��A�N�������͑I�𐧂Ƃ��邱�ƁB�i���@�P�W�R�`�P�X�W�j�i�p���j
�i���R�j
���^�����Ҏ���̐ӔC�ɂ����āA�Ŋz���v�Z���[�ł��鐧�x�������`�I�d�Ő��x�ɓK������̂ł���B�܂��A�ٗp�҂ɑ��āA�z��҂̃p�[�g�������Q�Ҏ蒠���̒�o�ȂǁA�v���C�o�V�[�̊J�������Ȃ���Ȃ�Ȃ����x�͉��߂�ׂ��ł���B
���ꂩ��́A�����ł̒��ŃR�X�g�Ԋ�Ƃɕ��S������ׂ��ł͂Ȃ��A����͓d�q�\���̕��y���i��}��A�m��\���������Ƃ���ׂ��ł���B
[10] �����ŊW�ɂ��āA���̂悤�ɂ��̎戵�������߂邱�ƁB�i�p���j
(1) �[�����ᐧ�x�́A���F�\���ł͂Ȃ��͏o���Ƃ��A���̓͏o������[���̓����F�߂邱�ƁB
(2) �l���Ƃ̐V�K�J�Ǝҋy�ѐV�ݖ@�l�ɂ��ẮA���̓͏o���u�J�Ɠ́v���́u�ݗ��́v�̖@������܂łɒ�o���ꂽ�ꍇ�ɂ́A�[���̓���K�p���J�Ƃ̓����͐ݗ��̓�����F�߂邱�ƁB
(3) �����ł̔[���̓��Ⴊ�F�߂����ɁA���^�̎x������l�������ł͂Ȃ��A�Ŋz�̊�������邱�ƁB�i���@�P�W�R�A�Q�P�Q�A�Q�P�U�A�Q�P�V�j
�i���R�j
(1) �[�����ᐧ�x�͏��F�\���ƂȂ��Ă��邪�A�����͏o���Ƃ��āA���Y�͏o������̓K�p��F�߂�ׂ��ł���B
(2) �l���Ƃ̐V�K�J�Ǝҋy�ѐV�ݖ@�l�ɂ��ē��ᐧ�x��݂��āA���̓͏o���u�J�Ɠ́v���́u�ݗ��́v�̖@������܂łɒ�o���ꂽ�ꍇ�ɂ́A�����`���҂̕X�ƐŖ��s���̉~���ȉ^�c��}��ϓ_����A�J�Ƃ̓����͐ݗ��̓�����[���̓���̓K�p��F�߂�ׂ��ł���B
(3) �p�[�g�Ј��̌ٗp�������Ă�������̏��l�����A�����Ŋz�����z�ȉ��̊�Ƃ́A���^���̎x������҂̐l�����킸�A�[���̓���K���K�p�\�ɂ���Ȃǂ̊��������ׂ��ł���B
[11] �����Ŗ@��P�Q�S���ɋK�肷��\�����i���m��\�����j�̒�o�������A�����ł̐\�������Ɠ���ɂ��邱�ƁB�i���@�P�Q�S�A�P�Q�T�A���@�S�T�j�i�p���j
�i���R�j
���m��\�����̒�o�������S�����Ƃ������Ƃ͈�ʔ[�Ŏ҂ɒm���Ă��Ȃ����A�[�Ŏ҂̎��S���o���鑊���ł̐\�������͎��m�O�ꂳ��Ă��Ă��邱�ƁA�������Y�̕�����ɐ\�����\�ƂȂ�_���l�����āA�����ł̐\�������Ɠ���ɂ��Ăق����B
[12] �F�\���̏��F�\���̊������A�����ɂ�鎖�Ə��p�̏ꍇ�ɂ͎��Ə��p�҂̊m��\�������܂łƂ��邱�ƁB�i���@�P�S�S�j�i�p���j
�i���R�j
�푊���l�̎��Ƃ����p����ɂ�����A�����l�Ԃł̋��c�ɏ\���Ȏ��Ԃ�K�v�Ƃ��邽�߁B
[13] �Ŗ����ɒ�o���ׂ��@�菑�ނɂ��ẮA���̂Ƃ�����߂邱�ƁB�i���@�Q�R�Q�A���K�X�R�A�j�i�p���j
(1) ���Y�������̒�o���x��p�~���邱�ƁB
(2) �@�蒲���̒�o�ɂ��ċ��^���̌����[�̓Y�t��p�~���邱�ƁB
�i���R�j
(1) �����ł̊m��\���ɂ��ẮA�K�v�Œ���̒�o���ނő����悤�ɂ��ׂ��ł���B���Y���Ƃ����l�������̎����z�ȏ�̎҂Ɉꗥ�ɋ��߂�̂́A�[�Ŏ҂ɑ��錠���ی�A�v���C�o�V�[�̊ϓ_������ł���B
(2) ���^�x���҂́A�s�����ɎґS���̋��^�x�����̒�o���s���Ă���B�����I�ɂ́A���łƒn���ł̈ꌳ���ɂ��A��o���ނ̏ȗ���}��ׂ��ł���B
[14] �F��m�o�n�ȊO�̂m�o�n�ɑ����t������t���T����F�߂邱�ƁB�i���@�V�W�A�P�Q�O�A�[�@�S�P�̂P�W�̂R�j�i�p���j
�i���R�j
���݂m�o�n�ɑ����t���T�����F�߂��Ă���͔̂F��m�o�n�݂̂ł���B�������Ȃ���F��m�o�n�̐��͌����Ă���A�قƂ�ǂ̂m�o�n�͓����t���̑ΏۂƂȂ��Ă��Ȃ��B�����̒c�̂́A�ŋ߂̌o�Ϗ̌�ނɂ��A�����I�ɔ��ɕN�����Ă���̂�����ł���B�����łm�o�n�̕��y��P�Ȃ闬�s�ɂ��Ȃ����߂ɂ́A���z�̏����݂���Ȃǂ̑[�u�͕K�v�ł͂��邪�A�����Ƃ��Ăm�o�n�ɑ����t������t���T���̑ΏۂƂ��ׂ��ł���B
[�O] �@�l�Ŗ@�W
[1] �������^�̑����s�Z���̋K������߁A������z���^�̌�����p�~���邱�ƁB�i�@�@�R�S�j�i�p���j
�i���R�j
��Ж@�ł́A�����ɑ��鋋�^�ɂ��Ă͔�p����F�߂Ă���B�����͉�Ќo�c�̍ō��ӔC�҂ł���A���̖����ɑ����V��������z�̌�������O�ꂽ�ꍇ�ɔF�߂��Ȃ��Ƃ����̂͐��x�Ƃ��ĕs�K�ł���B
[2] ���۔�ېłɂ��āA�Љ�ʔO��K�v�Ȏx�o�͉ېŏ��O�Ƃ��A��z�T�����x�z�ȓ��̎x�o�z�̂P�O���ېł��p�~���邱�ƁB�i�[�@�U�P�̂S�j�i�p���j
�i���R�j
���۔�ېł̎�|�́A��Ƃ̏��E����̗}���ɂ���Ɨ������邪�A�ېŋ����ɂ��A�Љ�ʔO��K�v�Ƃ����c����ɂ܂ʼnېł���邱�Ƃ̕s���������炩�ƂȂ��Ă���B����ɁA��z�T�����x�z���̒藦�ېł��A���̗��_�I�����ɖR�����A�p�~���ׂ��ł���B
[3] �ސE���t�������̑����Z�����x��n�݂��邱�ƁB�i�p���j
�i���R�j
�J�������A�ƋK�����ɂ��ސE���K��́A�����̍���J�������Ƃ��Ċ�ƂɂƂ��ċ����S���͂�����B���Y���ƔN�x�ɂ����Ĕ�������ސE���v�x���z�́A�����ɂ����Ďx�o�����W�R�������ɍ����B�܂��A�ސE���̋��z�͋K��ɂ�荇���I�ɎZ�o����A��Ɖ�v����ސE���t�������́A�����������Ƃ��Čv�シ�邱�Ƃ��v������Ă���B
�������A�@�l�Ŗ@�̍��m���ɂ����ẮA�ސE�Ƃ������t��������̓I�ɔ������Ă��Ȃ����߁A�ސE���t�������J���z�̑����Z���͔F�߂��Ă��Ȃ��B�܂��A�{���̊��Ԕ�p�ł���ސE���t�������ɂ��āA�ސE���ƔN�x�܂ő����Z�����s��Ȃ����Ƃ́A��Ƃ̐ŕ��S�̕������ɂȂ���Ȃ��B
�J������y�яA�ƋK�����ɂ��A�ސE���^�̎x���K����߂Ă���@�l�ɂ��ẮA���̋K��ɂ��ސE���^�v�x���z�̓��������z�̑����Z����F�߂�ׂ��ł���B
[4] ���Z���̒ʏ�̏����ېłɂ����Ďc�]���Y���Đŕ��S�����邱�Ƃ̂Ȃ��悤�ȑ[�u���s�����ƁB�i�@�@�T�X�j�i�p���j
�i���R�j
���Z�����ېł̔p�~�y�ђʏ�̏����ېłւ̈ڍs�ɔ����A�����@�l�����U�����ꍇ�Ɏc�]���Y���Ȃ��ƌ����܂��Ƃ��́A�����ꌇ�����̈��z�̑����Z�����F�߂��邱�ƂƂ��ꂽ�B�������Ȃ���A�܂݉v�̂��鎑�Y�p���ċ�s�ؓ���̕ԍςȂǂ��s�������ʁA���z�̎c�]���Y���c�����ꍇ�ɂ͊����ꌇ�����������Z������邱�Ƃ��Ȃ��A�c�]���Y����[�ł����߂��邱�ƂƂȂ�B����͒S�ŗ͂̂Ȃ��Ƃ���ɉېł��邱�ƂƂȂ邽�߁A�c�]���Y���Ĕ[�ŕ��S�����߂��邱�Ƃ̂Ȃ��悤�ȑ[�u�����ׂ��ł���B
[�l] �����Ŗ@�E�@�l�Ŗ@���ʊW
[1] ���z�������p���Y�ɂ��Ă̕K�v�o��A�����Z���̋��z������ׂĂR�O���~�����Ƃ���B�i���߂P�R�W�A�P�R�X�A�[�@�Q�W�̂Q�A�@�߂P�R�R�A�P�R�R�̂Q�A�[�@�U�V�̂W�j�i�p���j
�i���R�j
�Ő��̊ȑf�����l�����A�P�O���~�����̑����Z���A�Q�O���~�����̈ꊇ���p���x��p�~���A���������ĂR�O���~�����Ɉ�{�����ׂ��ł���B�܂��A���݂������R�O�O���~��P�p���A���A�P�v�I���x�Ƃ��ׂ��ł���B
[2] �d�b�������ɂ��Č������p���Y�Ƃ��ď��p���\�Ƃ��邱�ƁB�i���߂U�A�@�߂P�Q�j�i�p���j
�i���R�j
�d�b�������́A���`�Œ莑�Y�Ƃ��Č������p���ł��Ȃ����ƂƂ���Ă��邪�A���݂ł͓d�b���̈���`���͂Ȃ��A�ݔ���݂̂̕��S�ōςނ悤�ɂȂ��Ă��邽�߁A�s��ł̎�����l�͂Ȃ��B�]���āA���ݖ��`�Œ莑�Y�Ƃ��Čv�コ��Ă�����̂��܂߂āA���p���\�Ƃ��ׂ��ł���B
[3] ������Ƃ̐Ő��Ɋւ��A�ȉ��̑[�u���u����B�i�V�K�j
(1) �V���Ɏ��Ƃ��n�߂��ꍇ�i�@�l����������j�ɂ́A�����Ԓʏ�̏����ŁA�@�l�ł̈��z�����z����B
(2) �ߑa�n��ɍH�ꓙ��i�o�����ꍇ�ɂ́A���������z�ɒB����܂ł̏������z�ɂ��A�����Ԓʏ�̏����ŁA�@�l�ł̈��z�����z����B
�i���R�j
�ߎ��̌o�ϏɊӂ݁A���ɂ킪���o�ς̊�Ղ��Ȃ�������Ɗ������̂��߂ɁA���̂悤�Ȑ��x�荞�p�b�P�[�W�Ő���݂���ׂ��ł���B
[��] �����Ŗ@�W
[1] �����ł̉ېŕ����ɂ��āA�@�葊���������ɂ���Y�擾�ŕ������珃���Ȉ�Y�擾�ŕ����ɉ��߂�ׂ��ł���B �i���@�P�P�A�P�T�A�P�U�A�P�V�A�R�S�j�i�V�K�j
�i���R�j
��Y�擾�z�����z�ł����Ă��A��Y���z��@�葊���l���ɂ�蕉�S�����Ŋz�͈قȂ邱�ƁA�ꕔ�����l�Ɉ�Y�̘R�ꂪ�������ꍇ�Ȃǂł����ׂĂ̑����l�ɉe�����y�ڂ��ȂǁA�����I�ł͂Ȃ��[�����������B��Y�擾�ŕ����̓O��́A���x�̗p��������̎Љ�̕ω��ȂǂɏƂ炵�Ă��[�Ŏ҂̎�e�x�͍����ƍl������B
���̕����̗̍p�ƂƂ��ɑ����l�X�����̔��f�A�ӔC�̂��Ƃɔ[�t������I�𗘗p���邱�ƂƂ��āA�A�є[�t���x�̔p�~���v�]����B
[2] ���Y�]���̊�{�I�����ɂ��ẮA�@�߂ɂ����ċK�肷�邱�ƁB�i���@�Q�Q�j�i�p���j
�i���R�j
�����Ŗ@�Q�Q���ɂ͕]���̌���������߂��Ă��Ȃ����߁A������͒ʒB�Ɉˑ����Ă���B�����ŁE���^�łɂ����ẮA���Y�]�����ېŕW���ɋy�ڂ��e�����ɂ߂đ傫���A���̒ʑ����@�߂ɒ�߂��Ă��Ȃ����Ƃ́A�d�Ŗ@����`�̊ϓ_����e�F�ł�����̂ł͂Ȃ��B
[3] �㔭�I���R������ꍇ�̍X���̐����������A���R�����������Ƃ�m�������̗�������P�N�ȓ��Ƃ��邱�ƁB�i���@�R�Q�j�i�p���j
�i���R�j
���̋K��́A�㔭�I���R�ɂ�錠���~�ςƂ��Ă̋K��ł���A���̖ړI��B�����邱�Ƃ��ł���悤�A�葱���Ԃ��\���m�ۂ���K�v������B
[4] ���ꊔ���̔[�ŗP�\���x�̓K�p�������ɘa���邱�ƁB�i�[�@�V�O�̂V�̂Q�`�V�O�̂V�̂S�A�[�@�߂S�O�̂W�A�[�@�߂S�O�̂W�̂Q�j�i�p���j
�i���R�j
�[�ŗP�\�̓K�p������̂T�N�ԂɁA�펞�g�p�]�ƈ��̐����]�ƈ����N�Z���ɂ�����]�ƈ����̂P�O�O���̂W�O������鐔�ƂȂ����ꍇ�Ɍo�ώY�Ƒ�b�ɂ��F�肪��������A�[�ŗP�\���ł����A�P�\�Ŋz�̑S�z�Ɨ��q�ł����킹�Ĕ[�t���Ȃ���Ȃ�Ȃ����A������Ƃ̌o�c���͕s����ō�����Ɗ������R�O���ɖ����Ȃ��ł́A���̏������ێ����邱�Ƃ͓���Ǝv���邽�߁A�p�~���ׂ��ł���B
�o�ϊ����傫���ω����钆�ŁA���s�̂悤�Ɍٗp�����T�N�Ԃɂ킽��\�����邱�Ƃ͔��ɍ���ł���A���Ə��p�ɑ傫�Ȏx����������Ă���B�K�p�������ɘa���邱�ƂŁA������Ƃ̎��Ə��p��ϋɓI�ɐi�߂邱�Ƃ��ł���B
[5] ������p�̍T���Ώێ҂ɂ��āA�����[�ŋ`���ҁi���O���Z�ҁj�ɂ��čT����F�߂�B�i���@�P�̂R�A���@�P�R�j�i�V�K�j
�i���R�j
������p�͖��@�W�W�T���ɂ����u�������Y�Ɋւ����p�v�Ɋ܂܂�A�܂�������p�ɐ��������F�߂��Ă��邱�Ɓi���@�R�O�U�A�R�O�X�j�������Ƃ��Ĉ�Y����x�o���ׂ��ł���Ƃ����B
���S�����������l�������[�ŋ`���҂Ƃ������R�ō��T���ł��Ȃ��̂́A���ۉ��̐i�ޓ��{�ɂ����ĉېł̌��������������̂ł���B
[6] �Z��擾�����̑��^�ɌW�鑡�^�ł̔�ېŏ����̊ɘa��}��B�i�[�@�߂S�O�̂S�̂Q�A�[�@�߂S�O�̂T�j�i�p���j
�i���R�j
�ϗp�N���\�ɂ��ƓS�R���N���[�g�Z��p�Ȃǂ͂S�V�N�A�ؑ��Z��͂Q�Q�N�ł���A�ωΌ��z���̊����Z��̓K�p�v���́A�ωΌ��z���ȊO�̊����Z��̂Q�O�N�v���ɔ�ׂ�Ɖېł̌���������݂Ă���肪����B�ŋ߂̎���ł͒��Ã}���V�������w���A���t�H�[���̂����Z��Ƃ��Ďg�p����҂������B
�V�ϐk����{�s����ĂR�O�N���o�߂��A�s���Y�擾�łɂ����钆�ÏZ��̓���ł́A���a�T�V�N�P���P���ȍ~�̌����͐V�ϐk��ɓK�����Ă���Ƃ݂Ȃ����ƂɂȂ��Ă��邱�Ƃ��l������A�ωΌ��z���̊����Z��̓K�p�v�����ɘa���A�R�O�N�ɉ������Ă��悢�ƍl����B
�܂��A�i�C��Ƃ��āA�����Ă���e����̋��Z���Y���@��N�����A��N�w�𒆐S�Ƃ��Z��擾�𑣐i�ł���B
[�Z] ����Ŗ@�W
[1] �[�ŋ`���̖Ə����x��p�~���A�����Ƃ��Ă��ׂĂ̎��Ǝ҂��ېŎ��Ǝ҂Ƃ���B
�������A���K�͎��Ǝ҂̐\���[�Ŏ������S���l�����A���̉ېŊ��Ԃ̉ېŔ��㍂���N�ԂP,�O�O�O���~�ȉ��̏ꍇ�͐\���s�v���x������B
�ېŎ��ƎҁA�ƐŎ��Ǝ҂̋敪�����d���Ŋz�T���Ɋւ��āA�ȈՉېł�I�����邩�ǂ����́A�m��\�������܂łɔ[�Ŏ҂��I���ł��邱�ƂƂ���B�i���@�Q�@�P�S�A�X�A�R�V�j�i�p���j
�i���R�j
(1) �����Q�R�N�P�O���ɉ�v�����@����u����ł̉ېŊ��ԂɌW�����Ԃ��Ȃ��@�l�̔[�ŋ`���̖Ə��ɂ��āv�������\����A����Ԃɂ��ƐŎ��Ǝ҂肷�邱�Ƃɑ��ĉېʼn���s�ׂ��s�Ȃ��Ă��邱�Ƃ��w�E����Ă��邽�߁B
(2) ����ł̐ŗ��̈����グ���K�v���Ƃ̋c�_���Ȃ����Ȃ��ŁA����Ԃ̉ېŔ��㍂���P,�O�O�O���~�ȉ��ł���A�ېŊ��Ԃ̉ېŔ��㍂��������ł����Ă�����ł̔[�ŋ`���������Ȃ����Ƃ́A�������������������B�ԐڐłƂ����Ȃ�����A���ۂ͎��Ǝ҂��[�ŕ��S�����Ă���ʂ�����A�ېŊ��ԊJ�n���ɔ[�ŋ`���̗L���f����K�v�͂Ȃ��A���R�Ȃ���ېŎ��Ǝ҂Ƃ��ĔF�����A���̉ېŊ��Ԃ̉ېŔ��㍂���P,�O�O�O���~�ȉ��ɂȂ�ΐ\���s�v�Ƃ���B
(3) �ȈՉېł̑I�����A�����Ŋz�T���̌ʑΉ��A�ꊇ���z���Ɠ��l�Ɋm��\�����ɑI�����邱�ƁA�ȈՉېł�I�������ꍇ�ɂ͂Q�N�Ԍp�����邱�ƂňӐ}�I�ȉېʼn���s�ׂ�h�~�ł���B
(4) ���K�͎��Ǝ҂͊m�肵���ƐтɊ�Â��K���ɔ[�ł��ł���悤�ɂȂ�A�����̔[����������Ǝv����B���Ɍ���͌i�C���s����ŋƐї\��������Ȃ��߁A�s���̉e�����₷�����K�͎��Ǝ҂̕��S�����炰�邱�Ƃ��ł��A�d�Ő��`����Ɏ�����ƍl����B
[2] �u����y�ѐ��������̕ۑ��v�̗v���ɂ��ẮA�u���떔�͐��������v�Ɖ��߁A���Ǝ҂ɉߓx�̕��S�������Ȃ��悤�A����ɂ�����L�ڎ����̐�����}�邱�ƁB�i���@�R�O�G�A�[�@�W�U�̂S�j�i�p���j
�i���R�j
�u����y�ѐ��������̕ۑ��v�̗v���ɂ����ẮA����ւ̌`���I�ȋL�ڂ��K�v�Ƃ���A�\���I�Ɏ�������������L�������̒��ŁA���Ǝ҂̕��S���傫���Ȃ�\��������B���ؐ����d�����錩�n����́A�܂��u���������̕ۑ��v�𒆐S�Ƃ��Ĉʒu�t���A���������ɕs��������ꍇ�Ɍ���A����ւ̋L�ڂɂ���Ă��̕⊮�����߂邱�ƂƂ��ׂ��ł���B����̋L�ڗv�����ɘa���Ă��A�ېŎ���̎����̌��͏\���ɉ\�ł���B
����āA���������������O��Ƃ���L�������̎��Ԃɔz�������d���Ŋz�T�����x�����ׂ��ł���B
[3] ���Ԑ\�����x���������A�I���ɂ�蒆�ԂŔ[�łł���͈͂��g�傷�邱�ƁB�i���@�S�Q�j�i�p���j
�i���R�j
���s�̏���ł̔[�łɂ������ẮA���Ԑ\�����y�ъm��\�����ɂ܂Ƃ܂����[�Ŏ�������������K�v������B���K�͂̐V�K�[�ŋ`���҂̔����y�ьi�C�̒���ɂ��ؔ[���������邱�Ƃ�h�~���邽�߁A�[�Ŏ҂̑I���ɂ��Ώ۔[�t�Ŋz�ɂ�����炸���ԂŔ[�łł���͈͂��g�傷�ׂ��ł���B
[4] �@�l���Ǝ҂ɂ��āA�@�l�ł̊m��\�������̓�����Ă���ꍇ�ɂ����ẮA����ł̊m��\�������ɂ��Ă��A�ېŊ��ԏI����R�����ȓ��ɂ��邱�ƁB�i���@�S�T�j�i�p���j
�i���R�j
�@�l�ɂ��������ł̐\�������́A�@�l�Ő\���ƕ��s���čs��Ȃ��Ɛ��m�Ȍv�Z���ł��Ȃ��B�@�l�ł̊m��\�����̒�o�����������Ă���@�l�ɂ��ẮA�ېŊ��ԏI����R�����ȓ��Ƃ��ׂ��ł���B
[��] �n���Ŗ@�W
[1] �l���Ɛł̎��Ǝ�T���z��N�Q�X�O���~����N�T�O�O���~�Ɉ����グ�邱�ƁB�i�n�@�V�Q�̂S�X�̂P�O�j�i�p���j
�i���R�j
���Œ��̓��v�ɂ��A�킪���̃T�����[�}���̕��ϋ��^�z�́A�S�P�Q���~�i�����Q�Q�N�j�ƂȂ��Ă���B���̓_���l�����āA�K���z�܂Ŏ��Ǝ�T���z�������グ��ׂ��ł���B
[2] �s���Y�擾�łɂ��āA���̉��������邱�ƁB�i�n�@�V�R�̂V�j�i�p���j
(1) �������Ԃ��Q�O�N�ȏ�̔z��҂���̑��^�ɂ��擾�������Z�p���Y�ɌW��s���Y�擾�łɂ��ẮA��ېłƂ��邱�ƁB
(2) ���������Z�ېŐ��x�K�p�҂��A���葡�^�҂��瑡�^�ɂ��擾�����s���Y�ɌW��s���Y�擾�łɂ��ẮA��ېłƂ��邱�ƁB
�i���R�j
�v�w�́A���Y�������Œz���グ�Ă����Ɖ�����̂��Ó��ł���B�]���āA���̏������ɂ����čs��ꂽ�A�v�w�Ԃɂ�����s���Y�̈ړ]�ɂ��ẮA�s���Y�擾�ł��ېłƂ��ׂ��ł���B
�܂��A�����ɂ��s���Y�̎擾�ɂ��Ă͔�ېłɂȂ��Ă��邱�Ƃ���A���������Z�ېŐ��x�K�p�҂��A���^�����s���Y�ɂ��Ă��s���Y�擾�ł��ېłƂ��ׂ��ł���B
[3] ���������Z�ېŐ��x��K�p���ē��葡�^�҂��瑡�^�ɂ��s���Y���擾�����ꍇ�̈ړ]�o�L�̓o�^�Ƌ��ł́A�Q�O/�P�O�O�O�ł��邪�A�����ɂ��ړ]�Ɠ������S/�P�O�O�O�Ƃ���B�@�i�o�^�@�X�j�i�V�K�j
�i���R�j
���������Z�ېŐ��x��݂�����|�d���āA���^�̐ŗ��ł͂Ȃ������̐ŗ��Ƃ��ׂ��ł���B
[4] ���z�������p���Y�i�R�O���~�����j�ɂ��ẮA���p���Y�ɌW��Œ莑�Y�ł̑ΏۂƂ��Ȃ����̂Ƃ���B�@�i�n�@�R�W�R�j�i�p���j
�i���R�j
�@�l�ŁA�����łƓ���x�[�X�Ƃ��āA�����Ė@�l�ŁA�����ł̏��p�v�Z�̑ΏۊO����ēx�v�Z�����̑ΏۂɎ�荞�ނ��Ƃ͎������S���傫���B���x���ȑf�������S�̌y����}��ׂ��ł���B
[5] �Œ莑�Y�ł̖��`�l�ېŎ�`�������^���̏��L�҂ɕύX���邱�ƁB�i�n�@�R�S�R�j�i�p���j
�i���R�j
�n���Ŗ@�͌Œ莑�Y�ł̔[�ŋ`���҂Ɋւ��āA���`�l�ېŎ�`���̗p���Ă��邪�A�Œ莑�Y�ł̉��v�œI���i����l����A�^���̏��L�҂��łS���ׂ��ł���B
�����ŁA�䒠���`�l���^���̏��L�W�𖾂炩�ɂ��鏑�ނ��o�����ꍇ�ɂ́A�o�L�̈ړ]���Ȃ��Ƃ��A�^���̏��L�҂ɉېł���悤�ɐ��x�����߂�ׂ��ł���B
[6] �V�z�Z��ɑ���Œ莑�Y�ł̌��z�[�u�̓K�p�N�������������ƁB�i�p���j
�i���R�j
�Z���V�z�����ꍇ�ɁA�R�N�ԐŊz���P�^�Q�Ƃ���[�u���Ƃ��Ă���B�����A�V�z�̒����w�ωΏZ��̐Ŋz�̌��z�ɂ��Ă͓K�p�N�����T�N�ł���B�ǂ�������Z�p�Ɖ��Ƃ��Ă̐��i�͓��l�ƍl�����邽�߁A�K�p�N�����ɂ��ׂ��ł���B
[7] ���Ə��ł�p�~���邱�ƁB�i�n�@�V�O�P�̂R�O�`�R�Q�A�V�R�T�j�i�p���j
�i���R�j
���Ə��ł́A��Ƃ���s�s�ɏW�����邱�Ƃɂ��A�C���t���������̍����x�o�����Ƃ���n�݂��ꂽ�B���܂�A��s�s�ɂ͓s�s�@�\����������A���Ƃ������̎��Ə����W�����Ă��~���Ɋ�Ɗ������ł���悤�ɂȂ��Ă��Ă���B�Ő��n�݂̖ړI�͑��݂��Ȃ��Ȃ������ߔp�~���ׂ��ł���B
[8] �S���t�ꗘ�p�ł�p�~���邱�ƁB�i�n�@�V�T�j�i�p���j
�i���R�j
�S���t�ꗘ�p�ł̐Ŏ��͂T�W�R���~�i�����Q�P�N�x���Z�z�j�ł���n�������c�̂ɂƂ��Ă͏d�v�ȍ����ł���B�������A�S���t��̗��p�������ቺ�X���ɂ��钆�ł́A���̗��p���������z�ȏ���s�ׂƂ͌�����A������u�ґ�Łv�Ƃ��Ă̐��������S���t�ꗘ�p�ł̉ېō����͎����Ă��邽�ߔp�~���ׂ��ł���B
�Ŗ��s���Ɋւ��錚�c�E�v�]����
[1] �@�߉��ߒʒB�́A�����ʒB���܂߂Ă��ׂČ��J���邱�ƁB�i�p���j
�i���R�j
�s���̂�����ɂ��ẮA���̓����������߂��Ă���B�@�߉��ߒʒB�͂��ׂČ��J���A�[�Ŏ҂̗����ƐM����ׂ��ł���B
[2] �Ŗ����ɒ�o�������ނ̉{���y�ѓ��ʂɊւ���K������邱�ƁB�i�p���j
�i���R�j
�[�Ŏ҂̕X���l�����A�[�Ŏҋy�т��̈ϔC�����ŗ��m�ɐŖ����ǂɕۊǂ���Ă���\�������̉{���y�ѓ��ʂ��ł���悤�ɁA���Œʑ��@�ɋK�肷�ׂ��ł���B
[3] �s���Y�擾�ł̕��ی���𑁊��ɍs�����ƁB�i�p���j
�i���R�j
�l���͖@�l�̌��Z�ɂ����āA�K�Ȍv�Z���s���Ȃ����߁A�s���Y�擾��A�Q�����ȓ��ɐŊz���m�肷�邱�Ƃ��K�v�ł���B
[4] ���Y�]��������ߋ��S�N�ȏ�̕����{���ł���悤�ɂ��邱�ƁB�i�p���j
�i���R�j
���Y�]������͍��Œ��z�[���y�[�W�ɂĉ{���ł��A�Ŗ����ɍs���Ȃ��Ă����{�S���̘H�������ׂ邱�Ƃ��ł���ϕ֗��ł��邪�A�{���ł���͖̂{�N�x���܂߂R�N�x���݂̂ł���B����ɉߋ��̕]���z��m��K�v������ꍇ������Ǝv����̂ŁA�ߋ��S�N�ȏ㕪���{���ł���悤�ɂ��Ă��炢�����B�X�����̊��Ԑ����Ƃ̊֘A������A���Ȃ��Ƃ��ߋ��V�N���͉{���ł���悤�ɂ��ׂ��ł���B
 ���ӎ���
���ӎ���
��2012�֓��M�z�ŗ��m��